生活保護を受けるときの売却指導とは。持ち家を売却する流れも紹介
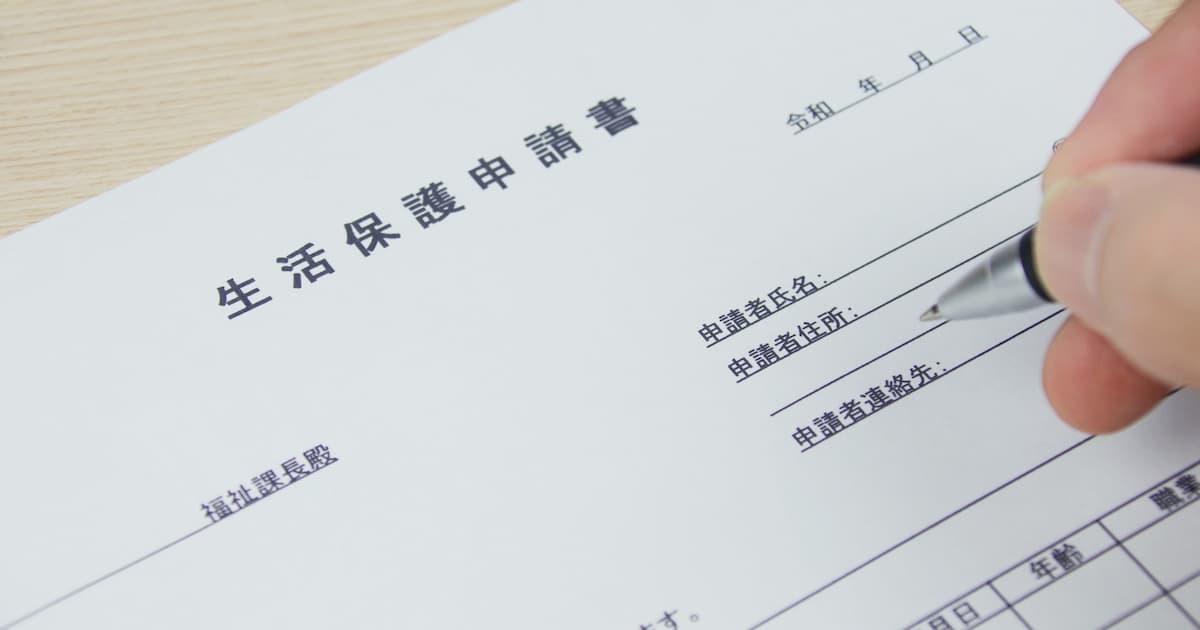
生活保護を受給するときに、役所から売却指導を受けることがあります。売却指導とは資産を売却して生活費に充てる案内のことを指しますが、現在住んでいる持ち家も売却指導の対象なのでしょうか。
ここでは、売却が必要なケースとそうでないケース、そして売却指導によって持ち家を売却するときの流れを紹介します。
もくじ
生活保護を受ける前に受ける売却指導とは?
生活保護を受けるに当たってはいくつかの条件があり、場合によっては保有している資産の売却を指導されることもあります。
ここでは生活保護の受給要件や、どういった資産が売却を求められるのかを簡単に解説します。
生活保護の受給要件
生活保護を受給するには、収入が最低生活費を下回っていることが条件です。最低生活費は国が定める基準で、地域や世帯人数などから必要な食費や住居費などを合計したものです。国が定める基準は厚生労働省「生活保護制度」より確認ができます。
収入と生活費の差額が保護費として支給されますが、ここでいう収入は給与だけではなく、保有資産や能力を活用して得られるものも含まれる点に注意が必要です。
つまり、たとえ給与が低くても、資産などの状況によっては保護費が受給できないケースがあるということです。具体的には、生活保護を受給するにあたり、以下の4つの要件を満たす必要があります。
- 資産を活用すること
- 能力を活用すること
- 扶養義務者からの扶養を活用すること
- 他の制度を活用すること
資産を活用すること
土地を持っていたり、自動車やバイクなどの処分価値のある資産を保有していたりする場合は、原則売却して生活費に充てることが求められます。
「親族などに贈与してしまえばよいのでは」と思うかもしれませんが、事実が判明すれば資産があるとみなされ、受給を解除されるおそれもあります。
能力を活用すること
病気やけがなどの事情がなく、働ける方が世帯にいる場合は能力に応じて働くことが求められます。
扶養義務者からの扶養を活用すること
両親や子ども、親族からの援助をできる限り受けることが求められます。そのうえで、収入が最低生活費を下回る場合に、生活保護が適用されます。
ほかの制度を活用すること
雇用保険や年金、各種手当など、受けられるものはすべて受けていることが前提です。つまり生活保護は最終手段ということです。
経済的自立のための資産活用
生活保護を受けるとき、保有している資産がある場合は努力して活用することが求められます。ここでいう活用は、必ずしも売却だけを指しているわけではありません。
たとえば、以下のような活用を実施するように指導を受けるケースがあります。
- 終身保険や養老保険などの貯蓄型の保険に加入している場合、資産性があるので解約返戻金を受け取る
- 持ち家があって部屋が余っている場合、その部屋を賃貸に出して収益化する
- すでに不動産を賃貸して収益を挙げている場合、家賃を引き上げる
さまざまな選択肢を考慮し、実践しても生活費を補うことが難しい場合、資産の売却という手段が提案されます。
売却が求められる不動産
売却できる資産としては、自動車やバイク、貴金属などが挙げられますが、資金の確保という点で最も効果的なのは、不動産です。特に以下のようなケースは不動産の売却を指導される可能性が高いです。
- 処分価値が利用価値に比べて著しく大きい
- 住宅ローンが残っている
- アパート・マンションなどの賃貸物件を所有している
- 不動産を相続した
処分価値が利用価値に比べて著しく大きい場合
マイホームについては基本的に保有することが認められていますが、「処分価値が利用価値に比べて著しく大きい」場合は売却が求められます。
具体的には、標準3人世帯の生活扶助基準額に、住宅扶助特別基準額を加えた額の約10年分とされており、金額としては約2,000万円が判断基準とされています。
標準3人世帯の生活扶助基準額に同住宅扶助特別基準額を加えた額の概ね10年分(約2千万円程度)を目処
つまり、資産価値が2,000万円を超える場合、基本的に売却の指導がされます。また、同居人数に対して見合わない家に住んでいる場合も売却の指導を受けるでしょう。たとえば、夫婦2人暮らしなのに、4LDK以上の家に住んでいる場合などです。
もちろん機械的に決まるわけではなく、実際には地域の状況や処分価値、世帯の事情などを勘案して判断されますが、参考値として頭に入れておくべきでしょう。
住宅ローンが残っている場合
住宅ローンを返済中の家を持っている場合は、原則生活保護の適用が認められません。これは、保護費が住宅ローンの返済に充てられるおそれがあり、税金で受給者の資産形成を手伝うことになってしまうためです。
残債が少ない場合などは例外的に受給が認められることもあるようですが、基本的には売却を指導されるケースが多いようです。
アパート・マンションなどの賃貸物件を所有している場合
貸家がある場合、家賃収入と売却による収入を比較して判断されます。
約3年以内とされる要保護推定期間の家賃収益が売却代金を上回らない限り、基本的には売却が指導されます。
不動産を相続した場合
親の死後、親名義の家を相続した場合も、その利用方法や資産価値によって売却の要否が判断されます。
居住用として活用しない場合、また居住用として住むとしても、処分価値が利用価値を著しく上回ってる場合は、売却を求められる可能性が高いです。さらに、不動産の売却益に関しては、支給済みの保護費に相当する金額を返還する必要もあります。
また、相続権を手放す相続放棄という手段もありますが、生活保護を続けたいがために相続放棄を行うことは原則認められないので、注意が必要です。
売却せずに保有が認められるケース
生活保護を受給する場合、原則不動産は売却を求められます。一方で、一定の条件を満たす場合は、売却せずに継続保有を認められることもあります。
ここでは売却しなくてもよいケースを具体的に説明していきます。
マイホーム
生活保護の目的は、受給者が自立した生活を営めるよう支援することです。受給者の持つあらゆる資産を取り上げてしまっては、受給者の自立に向けた試みを妨げてしまうおそれがあります。
そのため、処分価値が著しく大きな不動産は売却を求められる可能性があるものの、基本的には居住しているマイホームは保護受給中でも保有が認められます。
事業用の土地
田んぼや畑などの農業用の土地については、小規模なものであれば継続保有が認められやすいです。山林も、事業で使用している場合や、薪炭の自給目的で活用している場合は、保有を認められる可能性が高いです。
なお、これらもマイホーム同様、処分価値が利用価値を著しく上回っていないことが前提です。
資産性の低い相続不動産
生活保護の継続希望を目的とした相続放棄は認められません。一方で、資産価値の低い不動産を相続した場合は、相続放棄が容認される可能性があります。
そのような資産は、売却見込みが低く現金化が困難である一方、相続税や固定資産税などの維持費負担が予想され、相続放棄する合理性があると判断される余地があるためです。
売却指導を受けたときの流れ
売却指導があった場合、売却手続きは自分自身で進める必要があります。ここでは具体的な売却の流れ、査定を依頼する際の注意点などを解説します。
売却手続きは自分で
生活保護を受給するに当たっては、一定の例外はあるものの、基本的には保有している不動産の売却を指導されると考えておきましょう。特に、処分価値の大きさを判断する目安が約2,000万円というのは決して高い基準ではなく、住んでいるエリアによっては容易に抵触する可能性があります。
ここで注意したいのが、売却を指導されるといっても、役所が勝手に売却手続きを進めてくれるわけではないという点です。あくまで役所は売却の必要性を指摘するだけなので、手続きそのものは自分自身で手配していく必要があります。
不動産売却の流れ
不動産売却の大まかな流れは、以下のとおりです。
- 不動産会社に査定依頼をする
- 不動産会社と媒介契約を結ぶ
- 売却活動をする
- 見つかった買主と売買契約を結ぶ
- 不動産の引渡しと売却代金の受け取り
不動産を売却するとなった場合、まずその資産価値を正確につかむ必要があります。複数の不動産会社に査定を依頼して売却価格に納得できれば媒介契約※を結びます。
※媒介契約
不動産を売買する際に不動産会社に仲介を依頼する契約。媒介契約を結ぶことで買主の募集や契約書の作成などを行ってくれる。契約締結時には報酬として仲介手数料を支払う
媒介契約後、ポータルサイトなどを通じて広報活動を展開し、購入希望者が出てくれば売買契約に向けて交渉を開始します。買主と条件面で折り合いがつけば、引渡し・売買代金の受け取りへと進みます。
必要な経費としては、不動産会社に支払う仲介手数料、登録免許税や印紙税などの税金費用、設備の取り壊しなどの工事費用などが考えられます。
一括査定サイト「リビンマッチ」が便利
不動産の売却を検討したとき、まずは不動産会社に査定の依頼をします。しかし、不動産会社と一口にいっても、売買や賃貸など、得意とする分野はそれぞれ異なります。そのため同じ物件でも、会社が違えば査定価格や売却できるスピードに差が生じます。
より条件のよい不動産売却を行うには、不動産会社の比較検討が欠かせません。しかし、複数の不動産会社に相談することは手間と時間がかかります。そこで利用したいのが一括査定サイトの「リビンマッチ」です。
リビンマッチでは、売却したい不動産の情報を一度入力するだけで、同時に最大6社へ査定の依頼ができます。査定価格の比較ができるのはもちろん、査定結果の報告を受ける際に各社の対応も比較できます。
比較したうえで、信頼ができたり条件がよかったりする不動産会社を選ぶことで結果的に満足のいく不動産売却ができるでしょう。リビンマッチは完全無料で利用できます。ぜひ活用してみてはいかがでしょうか。

大手住宅メーカーの注文住宅販売や不動産テック企業の仲介業務に4年間携わり、不動産取引にかかわった件数は350件以上にわたります。2021年よりリビンマッチコラムの執筆・編集を担しています。皆さんが安心して不動産取引を行えるよう、わかりやすくリアルな情報を発信します。
この記事の編集者
 リビンマッチ編集部
リビンマッチ編集部
リビンマッチコラムでは、むずかしい不動産の事をできる限りわかりやすく、噛み砕いて解説しています。不動産に対するハードルの高いイメージ、とっつきにくい苦手意識を少しでも取り除いて、よりよい不動産取引のお手伝いをさせていただきます。
誤字脱字や事実誤認などございましたら、ぜひともご指摘ください。
運営会社:リビン・テクノロジーズ株式会社(東京証券取引所グロース市場)
人気ワード
マンション売却 (260) 戸建て売却 (189) 土地売却 (98) メリットとデメリット (72) アパート管理 (46) リスク (42) マンション管理 (40) 不動産投資 (39) ポイント (35) タイミング (26) 空き家 (25) 移住 (16) 利回り (15) 共有持分 (12) 競売 (12) 離婚 (11) 節税・減税 (10) 選び方 (7) 種類 (6) 工法 (5) イエウール (3) 老後 (3) リビンマッチ (2) 駐車場経営 (2) 戸建賃貸経営 (2) マンションの売却相場 (1) マンション相場の推移 (1) リノベーション (1) リースバック (1) マンション経営 (1)リビンマッチコラムを引用される際のルール
当サイトのコンテンツはどなたでも引用できます。 引用にあたって事前連絡などは不要です。 コンテンツを引用される際は、引用元が「リビンマッチ」であることを必ず明記してください。
引用ルールについて












