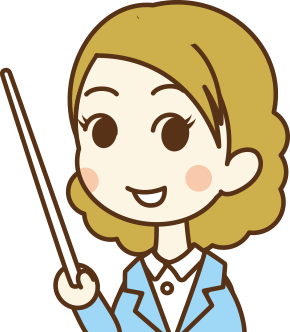家が売れたらすること!引き渡し後のトラブル対応を回避するには?

不動産売却では、売買契約の締結後もすることがたくさんあります。
また、引き渡しが完了し所有権が移転した後にトラブルが発生することも少なくありません。
その際に適切な対応をしなければトラブルがさらに大きくなってしまい、損害賠償請求の裁判を起こされることもあります。
この記事では、不動産を売却した際に必要な手順と、トラブルが起きた場合の対処方法について解説します。
もくじ
売買契約から引渡しまでの間にすること
不動産売買契約後、無事に引き渡しを迎かえるためには多くの手順を踏む必要があります。
買主は住宅ローンの借入や引っ越しの準備を行いますが、売主はどのような準備が必要なのでしょうか。
住宅ローンが残っていれば融資銀行へ連絡する
不動産を売却する際は抵当権を外す必要があります。
売却時に住宅ローンの返済が終わっていない場合、抵当権を外してもらうために融資銀行へ連絡し売却する旨を伝える必要があります。
引渡し時には融資銀行の担当者も同席し、所有権移転登記と同時に抵当権抹消時の手続きも進めます。
家屋内の整理と引っ越し
家屋内の整理をして、次の住居に持っていく家具を運び出します。
その際には、契約時に合意した付帯設備表と物件状況確認書をチェックし、残す物と持っていく物を間違えないようにしましょう。
また、設備が壊れていないかも再度チェックしておくと後のトラブル防止になります。
家具を運び出したら、清掃をして家をきれいな状態にしておきます。
必要書類の準備
引渡し時には買主から売却代金を受け取りますが、同時に所有権を移転する必要があります。
その際には必要な書類がそろっていなければ移転することができず、引渡しができなくなることもあるので注意が必要です。
登記識別情報通知(権利証)
登記識別情報通知とは、不動産の所有を証明する書類です。土地と家屋の2通ありますので、両方とも用意しましょう。
よく間違えられる書類に、全部事項証明書や不動産売買契約書があります。
両書類とも売主の氏名が記載されていますが、引渡しで有効なのは登記識別情報通知だけのため、注意しましょう。
紛失した場合であっても引渡しは可能ですが、その際には本人確認のため数万円の費用が発生することがあります。
印鑑証明書
印鑑証明書は市役所で発行ができますが、マイナンバーカードがあればコンビニで発行することもできます。
印鑑証明書カードを引渡し時に持参する売主もいますが、印鑑証明書カードではありません。必要なのは印鑑証明書になるので間違えないようにしましょう。
顔写真付き身分証明証
運転免許証やパスポートなど顔写真がついているものであれば問題ありませんが、持っていない場合は身分証明書を2種類準備する必要があります。健康保険証や年金受給証明証などが該当します。
引渡し時に来た売主が、間違いなく所有者であることを確認するために必要な書類です。そのため、所有者が仕事で忙しいから代理で妻が来たとしても引渡しできません。
必ず所有者本人か代理人の書類を持っている代理人が参加しましょう。
購入時に取得した書類
引き渡し時には家の仕様書や設備の取扱説明書を買主に渡します。
ただし、個人情報が分かる書類や不動産売買契約書などは別途保管する必要があります。
特に不動産売買契約書は確定申告時に必要となるため、誤って渡すことがないように注意しましょう。
契約内容によっては確定測量
敷地に杭がすべてそろっていなかった場合、契約内容によっては確定測量を行う必要があります。
確定測量とは、土地家屋調査士によって測量された図面に対し、隣地所有者と道路所有者の合意を得て行う測量です。
土地家屋調査士から確定図が発行され、正しい面積が判明します。
測量には売主も立ち会い、越境や問題がないかを確認しながら進めます。
引き渡し後は期限内に確定申告をする
不動産を売却して、利益が出た場合や、特例などを利用する場合は確定申告をする必要があります。
確定申告は売却する不動産や売主の事情によって細かく変わります。ここでは一般的な確定申告のステップを解説します。
必要な書類を準備する
不動産売却時の確定申告で共通して必要な書類は以下のとおりです。
- 譲渡所得内訳書
- 確定申告書B書式
- 確定申告第三表
上記書類は税務署で入手できます。次に紹介するのが、自分で用意する書類です。
- 購入時と売却時の不動産売買契約書コピー
- 購入時と売却時の諸費用領収書コピー
- 売却した不動産の全部事項証明書(土地と建物)
- 源泉徴収票と身分証明書、マイナンバーカード
購入時の売買契約書と諸費用があるかどうかで、支払う税金が数百万円違う場合もあります。相続で紛失している場合もありますが、なるべく多くの書類を準備しましょう。
申告書に記入をする
確定申告書は売主の事情によって記入方法が変わります。そのため、はじめての不動産売却で記入する場合は最寄りの税務署もしくは税理士に相談することがおすすめです。
確定申告の提出時期である2月16日〜3月15日は非常に混雑するため、時期をずらして早めの相談がおすすめです。
また、国税庁が運営する納税システム「e-tax」を利用して、インターネット上で行うのもおすすめです。
スマートフォンで完結できるため、まずはe-taxを利用し、分からなければ税務署に相談するという手順が効率的です。
納税する
不動産が購入時よりも高く売却できた場合には、譲渡所得税を納税する必要があります。
ただし、購入時よりも安い価格だったり、売却益が3,000万円以下となる居住用財産の売却であれば税金は発生しません。
確定申告をすると納税の有無が判明しますので、税金が発生していれば納税するようにしましょう。
引き渡し後に買主のトラブル対応をすることもある?
引渡した後もトラブルが発生することがあります。
すでに売却したのだから無関係だと言いたい所ですが、逃れられない義務がいくつかあります。
しっかりと想定していれば、販売活動の段階から対策してトラブルを避けることができます。
契約不適合責任に関する対応
売主は指定した期間の間、契約内容にそぐわなかった場合は対応する義務があります。
これを契約不適合責任といいます。
具体的には、雨漏りやシロアリなどの被害が見つかった場合です。不動産会社は被害を発見した買主から連絡を受けて、実際の状況を確認します。
そして契約不適合責任が認められた場合、買主は売主に対し以下の要求ができます。
- 費用減額請求
- 原状回復請求
- 契約解除
- 損害賠償請求
売主にとっては大きな負担になるため、どのような対処が適切なのかは担当者に相談して決めるようにしましょう。
契約不適合責任は決して珍しくないトラブルですので、十分な注意が必要です。
契約内容に勘違いがあった
引っ越し時に持って行ってはいけない家具類を運び出してしまったり、逆に置いていってしまったりというトラブルもよく起きます。
不動産売買契約時に、売主は付帯設備表と物件状況確認書を買主に提示し、置いていく家具類や故障・修理箇所について合意を得ます。
そのため、引っ越し時には書類に沿った家具類の撤去や残存をする必要があります。
告知漏れがあった
引き渡した不動産に対する告知漏れがあった場合、売主は買主の要求に応じる必要があります。
不動産売買は信義誠実の原則に従い誠実に行わなけばならないという規定があります。
具体的には、下記のように買主にとって不都合となる要素を隠してはいけません。
- 周辺での事件
- 隣地トラブル
- 将来確定しているゴミ処理場建設
買主は家を購入し新しい生活をスタートします。そのためトラブルが続いた家に住む買主のストレスは大きく、買主の信頼を裏切ることになります。そうならないよう、引き渡す不動産については大小関わらず、気になる点はすべて告知しましょう。
しかし、居住している売主は買主にとって不都合となる点に気づかない場合も多いです。告知すべき事項を見落とさないために、担当者にもしっかりとチェックしてもらいましょう。
不動産売却は優秀な担当者選びが重要
不動産売却では、トラブルの中でも特に引渡し後に起きるトラブルの方が大きく発展する傾向があります。
しかし、不動産会社の担当者が優秀であれば、解決できるケースが多いです。
経験豊富な担当者であればトラブルを予測し、売主へリスクを伝えることでトラブルを未然に防ぎます。
一方、未熟な担当者は契約を急ぎ、重大なポイントを売主にも買主にも伝えないことがあります。
そのため、不動産売却では優秀な担当者と出会えるかどうかがポイントです。
理想の担当者を探すためには、一括査定サイトを利用しましょう。一括査定サイトは同時に複数の不動産会社へ査定依頼ができます。たとえば、5社に査定依頼を出せば、必然的に5人の担当者とコンタクトを取ります。
査定額が分かるだけでなく、担当者の比較検討も可能です。トラブルで悩まない不動産売却を進めるためにも、一括査定サイトを利用しましょう。

大手住宅メーカーの注文住宅販売や不動産テック企業の仲介業務に4年間携わり、不動産取引にかかわった件数は350件以上にわたります。2021年よりリビンマッチコラムの執筆・編集を担しています。皆さんが安心して不動産取引を行えるよう、わかりやすくリアルな情報を発信します。
この記事の編集者
 リビンマッチ編集部
リビンマッチ編集部
リビンマッチコラムでは、むずかしい不動産の事をできる限りわかりやすく、噛み砕いて解説しています。不動産に対するハードルの高いイメージ、とっつきにくい苦手意識を少しでも取り除いて、よりよい不動産取引のお手伝いをさせていただきます。
誤字脱字や事実誤認などございましたら、ぜひともご指摘ください。
運営会社:リビン・テクノロジーズ株式会社(東京証券取引所グロース市場)
人気ワード
マンション売却 (260) 戸建て売却 (189) 土地売却 (98) メリットとデメリット (72) アパート管理 (46) リスク (42) マンション管理 (40) 不動産投資 (39) ポイント (35) タイミング (26) 空き家 (25) 移住 (16) 利回り (15) 共有持分 (12) 競売 (12) 離婚 (11) 節税・減税 (10) 選び方 (7) 種類 (6) 工法 (5) イエウール (3) 老後 (3) リビンマッチ (2) 駐車場経営 (2) 戸建賃貸経営 (2) マンションの売却相場 (1) マンション相場の推移 (1) リノベーション (1) リースバック (1) マンション経営 (1)リビンマッチコラムを引用される際のルール
当サイトのコンテンツはどなたでも引用できます。 引用にあたって事前連絡などは不要です。 コンテンツを引用される際は、引用元が「リビンマッチ」であることを必ず明記してください。
引用ルールについて