【状況別】家は生前贈与と相続、どちらが得?時期を決める3つのポイント
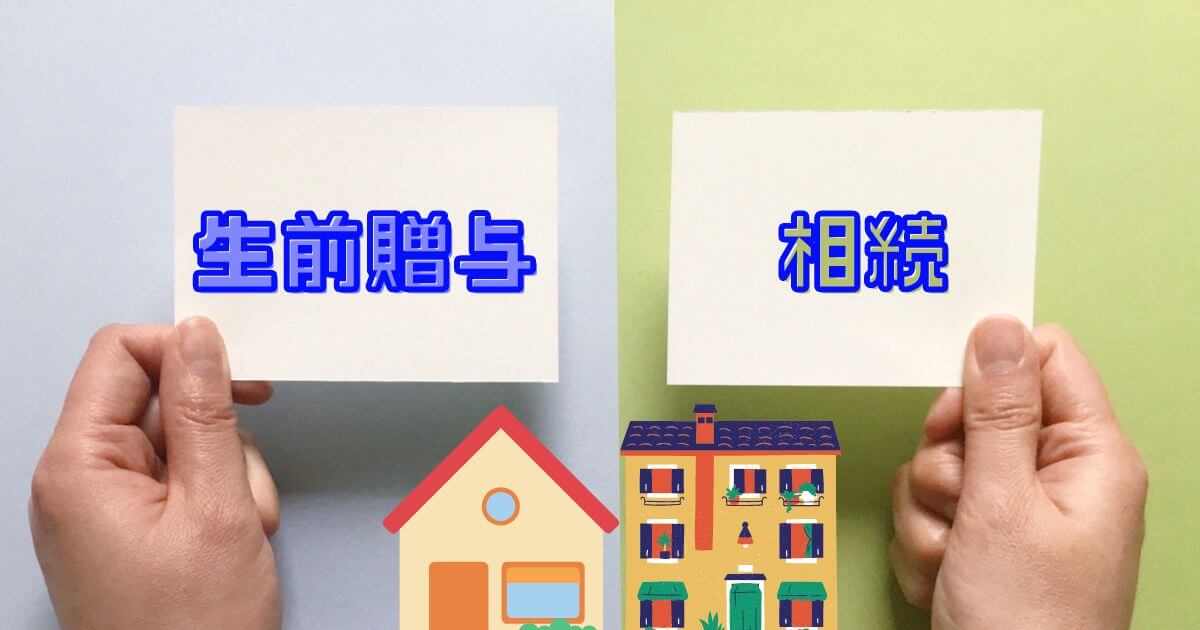
持ち家を所有しているなら考えておいたほうがよいのが、生前贈与すべきかどうかです。自分が亡くなる前に生前贈与したほうが得なのか、亡くなった後に相続してもらったほうが得なのか、事前に確認しておくことで家族の負担を減らせます。
一概に生前贈与と相続どちらがよいとは言い切れませんが、「どちらがより得をしそうか」状況別に推測することは可能です。どちらにすべきか、一緒に確認してみましょう。
もくじ
基本的に相続のほうが納税負担は少ない
ほとんどのケースでは、家を譲るなら相続のほうが納税負担は少なくなります。その理由を見ていきましょう。
その理由とは?税金の差をシミュレーション
たとえば以下のような例で、家を生前贈与した場合と相続した場合を比べてみます。
- 〈家族構成〉夫・妻・娘・息子の4人家族
- 〈財産〉現金:2,000万円・家(土地と家):3,000万円の相続税評価額
生前贈与の場合は「暦年贈与」と「相続時精算課税」のどちらかを選んで財産を譲ります。特に申請がない場合は暦年贈与の扱いです。
毎年110万円までは、贈与税はかからないと耳にしたことがあるかもしれませんが、これは暦年贈与です。小分けにできる現金の贈与に向いている方法です。
相続時精算課税は2,500万円まで一気に財産を渡せます。2,500万円を超えた分の贈与税は一律20%かかり、2,500万円までの財産に対しては、相続のときに相続税として計算されます。シミュレーションのように家など、小分けにできない不動産の贈与におすすめの方法です。
ただし、自分が60歳以上の父、母、祖父母であり、家を譲り受ける人は18歳以上の子や孫である必要があります。また、3,000万円の家を生前贈与するときは、3,000万円−2,500万円=500万円×20%=100万円の贈与税を支払うことになります。
一方、相続で配偶者や子どもなど相続人に財産を譲るときは、税金のかからない枠があります。「基礎控除」と呼び、以下の計算式で計算できます。
相続税の基礎控除=3,000万円+法定相続人の数×600万円
この家族に当てはめると、夫が亡くなった場合以下のように計算します。
相続税の基礎控除=3,000万円+3人×600万円=4,800万円
つまり、シミュレーションでは家に限らず全財産を妻や子どもたちに譲っても、4,800万円からはみ出た200万円に対してのみ相続税がかかります。1,000万円以下の相続財産にかかる税率は現在10%なので、このケースの相続税は20万円です。
相続税=200万円×10%=20万円
参考:国税庁「No.4155 相続税の税率」
さらに、相続のときは特例などを使って相続税額を少なくできる可能性もあるため、このケースでは納税額がゼロになる可能性が高いのです。
また、贈与税や相続税以外にも、家を登記するときにかかる「登録免許税」や家を取得したことに対してかかる「不動産取得税」を支払う必要があります。生前贈与では相続に比べて、この2つの金額が10倍以上高くなります。
生前贈与では登録免許税に家の価格の2%、不動産取得税に1.5〜4%かかるため、合計で3.5〜6%もの税金を支払う必要があります。先ほどの3,000万円の家の場合は、約105万円〜180万円を贈与税以外にも支払う必要があるのです。
一方、相続の場合は登録免許税が0.4%、不動産取得税はゼロです。3,000万円の家の場合の登録免許税は12万円となり、生前贈与の場合と比べると大きな差です。
シミュレーション結果を表にまとめると以下のようになり、納税額は相続のほうが圧倒的に少なくなります。
| 税金 | 生前贈与(相続時精算課税)(万円) | 相続(万円) |
|---|---|---|
| 贈与税/相続税 | 100 | 最大20 |
| 登録免許税 | 60 | 12 |
| 不動産取得税 | 45〜120 | なし |
| 合計 | 205〜280 | 32 |
法定相続人が少ないなら、生前贈与したほうがよいケースも
「すでに配偶者がいない」「子どもがいない」などで法定相続人が少ない場合は、生前贈与をしたほうがよいケースもあります。なぜなら相続税は、所得税の累進課税と同じで、財産が多くなるほど支払う率が高くなっていくからです。
相続人が配偶者だけ、もしくは子ども1人だけの場合は基礎控除も3,600万円になり、家を含む相続財産が5,000万円の場合、相続税額は160万円です。
- 法定相続分による取得金額=5,000万円−基礎控除の3,600万円=1,400万円
- 法定相続分による取得金額=税金に算入する額=1,400万円×15%(相続税の速算表にもとづく税率)=210万円
- 相続税=税金に算入する額の210万円-相続税の速算表にもとづく控除額の50万円=160万円
参考:国税庁「No.4155 相続税の税率」
納税額だけで見るとそれでも相続で家を譲ったほうが少ないのですが、相続が起こってから登記を変更するには出生からの戸籍を集めるなど必要書類も多くなります。
また、たとえば妻と兄弟が相続人の場合は、妻が夫の兄弟全員から家を相続する承諾書を取り付けなければいけません。
万が一、兄弟の中に「私にも相続する権利がある」と主張して承諾しない人が出てくると、納税額の差以上の負担を強いられてしまう危険性があります。
なお、このような場合は婚姻期間が20年以上の夫婦に限り、住むための家であれば2,000万円まで贈与税を支払うことなく、妻に譲れる特例があります。納税額だけで比較すると相続のときに家を譲ったほうが得かもしれませんが、親族間で揉めてしまうと、夫亡きあと妻が住む家を失ってしまうおそれがあります。
参考:国税庁「No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」
必ず家を渡したい人がいる場合や、相続人間の仲があまりよくない、面識がない、など揉める危険性がある場合は、納税額の大小だけでなく生前贈与を視野に入れることも必要でしょう。
生前贈与と相続の違い
生前贈与と相続の違いについて、明確に説明できる人は意外と少ないです。どちらが得か判断するためにも、違いをここで再認識しておきましょう。
生前贈与は生きているうちにプレゼントすること
生前贈与とは、生きているうちに持っている財産や、所有している権利を誰かにプレゼントすることです。自由にどのくらいの財産を誰に渡すか、どの権利を誰に譲るかを指定できるのが特徴です。
そのため、自分を介護してくれている人に感謝のしるしとして住宅をプレゼントしたいといったケースでは、生前贈与を選択される方が多い傾向です。しかし、状況によっては贈与を受ける人は贈与税などの税金を支払う必要があります。
相続は死亡後に自分のすべての財産や権利が引き継がれること
相続とは、亡くなった時点で財産や所有している権利が誰かに引き継がれることです。相続は自分の死後に発生するので、遺言などの特別な決めごとをしていないと、自分の思いに沿って財産を分けてもらえないかもしれません。
最近では、子がいない夫婦も増えているので、兄弟間の分け方で揉めるケースも増えています。
財産を譲り受ける人は相続税を支払う必要がありますが、夫婦間や子どもなどの相続人は一緒に財産を築いてきた特例として、税金が免除される財産額の枠があります。特に配偶者は共同財産の意味合いが強いので、何億の資産があったとしてもその半分までは税金がかからない特例もあります。
相続は故人が亡き後も残された家族が生活を営んでいけるよう、財産を引き継いでもらう制度です。
生前贈与のほうが得な可能性が高い状況
生前贈与のほうが得な可能性が高い状況は、次のとおりです。
- 相続争いに発展するリスクが高い
- 相続後に、家を引き継いで住んでほしい人がいる
- 売却しない場合で、贈与後に家の価値が上がる可能性が高い
- 都市部の家と地方の土地など複数の不動産を所有している
- 住み替えや介護に備えて、家を売却する可能性がある
相続争いに発展するリスクが高い
相続では、不動産が火種となって相続争いに発展するケースが珍しくありません。現金なら平等に分けられますが、家は平等に分けることが難しいからです。仲のよかった家族でも、財産の分け方をめぐって何年も裁判しているという話をよく耳にします。
たとえば、以下のケースで考えてみましょう。
- 〈家族構成〉自分・妻・娘・息子の4人家族
- 〈財産〉現金:2,000万円・家:3,000万円
自分が亡くなったことにより、妻が今後も住み続けるために3,000万円の価値がある家を相続しました。娘と息子で現金を1,000万円ずつ分けたところ、娘が法定相続分である財産(不動産)の4分の1はもらう権利があると主張し、妻(母)に250万円の支払いを求めました。
現金は娘、息子それぞれで1,000万円分取得したので、妻がもらった3,000万円分の不動産のうち、1,000万円分は妻の分です。残りの2,000万円の不動産を兄弟間で分けると、2,000万円÷2=1,000万円で1,000万円×法定相続分の4分の1=250万円分が1,000万円にプラスで娘が本来もらえるはずの財産です。
しかし、妻の立場からすると現金をすべて子どもたちに渡しているうえに、自分の貯蓄から250万円を娘に渡すことになるので、かなりの痛手です。
このように一般的な家庭でも相続で揉めることは多いので、事前に妻に生前贈与しておくことが有効な場合もあります。
相続後に、家を引き継いで住んでほしい人がいる
相続後に、相続人ではない人が自分の家に住む予定がある場合は生前贈与のほうがよい可能性があります。
相続は遺言などを残さない限り、自分の死後に配偶者や子など相続人が集まって話し合いをし、財産の分け方を決めます。
たとえば、自分の死後に配偶者は老人ホームに入りたい、子どもたちはすでに持ち家があるといった場合、即売却を検討するよりは、成人した孫に家を譲りたいと考える方がいます。
子どもが健在の場合、孫は相続人ではないので、死後の話し合いで必ずしも自分が渡したいと思っていた孫に家を渡せるとは限らないでしょう。
さらに相続で孫に財産を譲る場合は「相続税2割加算」という、おそろしい制度が待っています。子どもに譲れば100万円で済んだ相続税が、相続人ではない人に譲ると120万円になってしまうのです。
孫に譲る以外でも、内縁の妻や親しい友人など、親族関係ではない人に家や財産を譲りたいときは相続税2割加算の対象です。
売却しない場合で、贈与後に家の価値が上がる可能性が高い
住んでいた家の土地の価値が上がるのは嬉しいことですが、かなり高騰しそうな人気の土地は生前贈与を検討する余地があります。
たとえば、現時点では1,000万円の価値がある家を、贈与を受ける年の年齢が18歳以上の子どもに生前贈与するとします。この場合の贈与税は、170万円ほどで済みます。
贈与税=(1,000万円-基礎控除の110万円)×相続税の速算表にもとづく税率30%=267万−相続税の速算表にもとづく控除額の90万円=177万円
参考:国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」
しかし、とてもよい立地にあり自分が亡くなって相続が発生したときに3,000万円など価値がかなり上がっていた場合、現預金などほかの財産と合わせると相続税が高額になる危険性があるのです。
過去には、10年で地価が30%上昇したケースもあります。現金などほかの財産を合算した額が、相続で税金がかからない枠に収まるなら考慮する必要性は少ないでしょう。
しかし、ほかの財産を合わせた額が数億などかなり多くなる場合は、相続のときに計算の元になる金額が増え、相続税率が高くなる危険性があります。
都市部の家と地方の土地など複数の不動産を所有している
生前贈与を検討したほうがよい例が、自分の家は比較的都市部にあるものの、地方に親から引き継いだ家や土地を所有しているケースです。
家族構成にもよりますが、自分の家の評価額は1.5億円、地方の土地は300万円ほどの評価額だった場合、相続財産から差し引ける基礎控除を差し引いても、1億円以上に対して相続税がかかってしまうケースが多々あります。
生前贈与で事前に地方の土地を子どもに譲っておけば、300万円ほどの価値なら税率は10%のため、贈与税は少なくて済みます。
しかし、まとめて相続した場合は、家の1.5億円という金額に引っ張られて、15%や20%、分け方によっては30%の税率を課されてしまう危険性があるのです。
住み替えや介護に備えて、家を売却する可能性がある
今後、家を売却する可能性がある場合も生前贈与を検討したほうがよいでしょう。これからどんどん増加していくといわれている認知症の問題も、相続に大きく関わってきます。
万が一、自分が認知症になってしまった際、介護費用の捻出のために家族が家を売却したいと思っても、名義が自分である場合は簡単に売却できません。
名義が認知症になってしまった自分のままで売却するには、家庭裁判所で成年後見人を立てる必要があるため、時間もお金もかかり、家族が苦労することになります。
特に最近は資金に困っていなくても、車が必要な地域の家を売却して利便性のいい駅前のマンションに住み替えたり、夫婦でサービス付き高齢者住宅に入居したりする方も増えています。
将来的に家を売却する可能性があるときは、生前贈与しておくのもひとつの方法です。
相続のほうが得な可能性が高い状況
相続のほうが得な可能性が高い状況は、次のとおりです。
- 家の所有者が高齢など3年以内に亡くなるリスクが高い
- 贈与後に家の価値が下がる危険性が高い
- 土地の評価額が80%オフになる小規模宅地の特例が使える
- 家を含めた財産の総額が税金のかからない範囲である
家の所有者が高齢など3年以内に亡くなるリスクが高い
配偶者や子どもに生前贈与で家や現金を前もって譲っても、譲ってから3年以内に万が一亡くなってしまうと、譲った財産はすべて相続でもらったものと見なされ、改めて相続税を計算します。特に生前贈与する年齢が高齢になってからの場合は、注意が必要です。
ただし、生前贈与をした相手が相続人ではない場合は、3年以内の贈与がなかったものと見なされる特例は適用されません。孫や姪・甥、友人などに生前贈与する場合は3年以内に亡くなっても、そのまま有効になります。
ただし、令和6(2024)年1月1日以降は3年以内だった贈与無効の期間が、7年間に延長されることが決まっています。元気なうちに若い現役世代に財産を譲っていくことが政府の狙いのようです。
贈与後に家の価値が下がる危険性が高い
相続のときの不動産の評価額は、死亡したときの時価で計算します。一般的に、時価の約8割が相続税の計算のときに使われる評価額です。
死亡時に3,000万円の時価の土地なら、約2,400万円を現金などの相続財産にプラスします。
価値が下がる危険性が高い家を、高い贈与税を払って生前贈与したとします。相続のときに価値が下がっていたら、「いまなら税金を払わなくて済んだのに」という事態になりかねません。
相続がいいか生前贈与がいいか判断するには、まずは家の評価額を知ることが大切です。
土地の評価額が80%オフになる小規模宅地等の特例が使える
小規模宅地等の特例は、土地の評価額を80%オフにしてくれるありがたい制度です。東京都内などの都心部を中心に、土地が2億や3億に高騰してしまったため、相続税を払えず、配偶者であるにもかかわらず住む家を失う事態が発生したために作られた制度です。
小規模宅地等の特例を使う対象となる土地は、自宅用の土地と事業用の土地、故人が持っていた賃貸物件などがありますが、今回は自宅の場合を考えます。
配偶者や子どもが住む家を失うことを回避する制度のため、適用の条件は厳しめです。適用範囲は330㎡までのため、約100坪です。約100坪を超える面積に対しての評価額は、減額されません。
また、配偶者か家の所有者の同居していた親族が引き継ぐ場合に限り、制度が適用されます。特例として、配偶者がいない場合は別居の子どもなども対象ですが、その子どもが持ち家を持っていない場合に限る、など制約があります。
しかし、小規模宅地等の特例が適用されれば、本来3,000万円の評価額の土地が600万円になるという絶大な影響力があるので、これが適用される場合にはぜひ利用したい制度です。
-
- 小規模宅地等の特例=土地の評価額 × 減額割合=減額後の評価額
- 小規模宅地等の特例による減額後の土地の評価額=3,000万円(評価額)×20%(100%-80%= 20%)=600万円
家を含めた財産の総額が税金のかからない範囲である
基本的なことですが、相続には「基礎控除」という、そもそも相続税がかからず、申告も不要な財産の範囲があります。
夫、妻、娘、息子の4人家族で夫または妻が亡くなった場合は、相続人が3人となるため、基礎控除は4,800万円です。
財産が現金2,000万円、家の評価額2,000万円など4,800万円を上回らない場合は、わざわざ贈与税を払って生前贈与する必要性は少ないでしょう。ただし、この場合は誰に家を引き継いでほしいのか、そのほかの現金はどのような割合で誰に引き継いでほしいのか、遺言でしっかり残すことが大切です。
家を譲るのは生前?死後?判断するのに欠かせない3要素
生前か死後のどちらがよいのか判断するには、以下の3要素が欠かせません。確認したうえで自分や家族の状況を洗い出せば、あなたや家族にとって生前か死後、どちらが得か答えられるでしょう。
制度の適用可否
以下の制度の適用可否は、生前贈与か相続どちらにするかの判断目安になります。
- 相続時の小規模宅地等の特例
- 生前贈与時の婚姻期間20年以上の配偶者への住宅贈与
小規模宅地等の特例が適用される場合は、家の土地の評価額が80%オフで計算されるため、多額の相続税を支払う危険性は格段に減ります。残された配偶者に家を引き継ぐ場合や、同居の子どもに引き継ぐ場合は相続を検討する余地がおおいにあるでしょう。
また、全体の相続財産を減らすために家の名義は配偶者にしておきたいという意見も多くあります。特に60代以上では、妻が専業主婦で貯蓄などの財産はほとんど夫名義のものしかない方もよくいます。この場合は、生前贈与を検討したほうがよいかもしれません。
たとえば、夫名義の財産が1億円で妻名義の財産はほぼない場合、2,000万円の家を生前贈与しておけば、夫8,000万円、妻2,000万円と偏りを減らせます。制度の対象は、婚姻期間20年以上で内縁の妻は対象外となるため、注意しましょう。
家以外の純資産額
生前贈与か相続かどちらが得かを考える際、まず把握したいのが全体の財産額です。家の評価額を知ることはもちろん、家以外の純資産額もしっかりと把握しましょう。現金以外にも、株や投資信託、会員権、骨董品なども資産に入ります。
すべての財産が基礎控除の範囲内なら、贈与税を支払って生前贈与する必要はないかもしれません。反対に多額の相続税がかかりそうな場合は、前述の特例を使って、生前に婚姻期間20年以上の配偶者に家を譲って、自分の財産額を減らしておく対策が取れます。
財産額を把握しなければ、万が一、介護が必要になった場合に家をリフォームしたり、施設に入る費用が捻出したりできるのか、捻出してもかなり余裕があるのかなどもわかりません。
費用が不足しそうな場合は、家を売却する準備として家を譲って、名義を変更しておくのも準備のひとつとなるため、まずは自分の純資産額を把握しましょう。
家の評価額
現金に比べて、どれだけの価値があるのかわかりにくいのが家の評価額でしょう。生前贈与、相続のいずれの場合も、毎年発表される「相続税路線価」を把握することで、家の土地の評価額を調べられます。ここで調べた家の土地の評価額に70%をかけたものが、おおよその相続税評価額です。
財産評価基準書路線価図・評価倍率表「令和5年分財産評価基準を見る」
家自体の評価額は、毎年送られてくる固定資産税の納税通知書で把握できます。納税通知書に記載のある固定資産税評価額が、相続税評価額です。相続税評価額は相続税の課税基準となる価格で、通常は実勢価格よりも低く設定されます。
毎年変更され、都市開発があると大幅に変更される危険性があります。家の評価額は定期的にチェックしましょう。
どちらが得か判断するには家の評価額と売却価格の差が重要
家の評価額、つまり建物とその土地の評価額と売却価格には差があります。評価額は、不動産鑑定士が市場価値や将来の収益などを考慮して算出したもので、不動産の評価の際には税金(贈与税や相続税)の基準となります。
一方、売却価格は実際の売買契約が成立した時点での取引価格です。売却価格が高ければ高いほど、売主にとって利益が増えます。
贈与税および相続税は、不動産の評価額に応じて計算されることがありますが、それぞれの税金は評価額によって異なります。
たとえば、家の評価額が高くても売却価格が低い場合は、生前贈与すると贈与税が高くなる危険があります。逆に家の評価額が低くても売却価格が高い場合は、相続すると相続税が低くなる可能性もあります。
不動産の評価額と売却価格の差を知るには、一括査定サイトを利用するのがおすすめです。最大6社の不動産会社から査定を受けられるので、査定結果を比較することで、より正確な家の価値を把握できます。
この記事の編集者
 リビンマッチ編集部
リビンマッチ編集部
リビンマッチコラムでは、むずかしい不動産の事をできる限りわかりやすく、噛み砕いて解説しています。不動産に対するハードルの高いイメージ、とっつきにくい苦手意識を少しでも取り除いて、よりよい不動産取引のお手伝いをさせていただきます。
誤字脱字や事実誤認などございましたら、ぜひともご指摘ください。
運営会社:リビン・テクノロジーズ株式会社(東京証券取引所グロース市場)
人気ワード
離婚で家を財産分与 (27) 老後の住まい (24) 売れないマンション (16) 一括査定サイト (15) 離婚と住宅ローン (13) 海外移住 (11) 訳あり物件 (11) 家の売却 (11) 家の後悔 (10) 不動産高く売る (9) 実家売却 (9) マンション価格推移 (8) マンションの相続 (8) 移住 (7) アパート売却 (7) 不動産会社の選び方 (6) マンション売却の内覧 (6) 家の価値 (6) 離婚と家 (6) 売れない家 (5) お金がない (5) 空き家売却 (5) 離婚準備 (5) 離婚と家売却 (5) 農地売却 (4) 近隣トラブル (4) マンション買取 (4) 家の解体費用 (4) 売れない土地 (3) マンションか戸建てか (3) サブリース (3) イエウール (3) 不動産価格推移 (3) リビンマッチ評判 (2) シンガポール移住 (2)リビンマッチコラムを引用される際のルール
当サイトのコンテンツはどなたでも引用できます。 引用にあたって事前連絡などは不要です。 コンテンツを引用される際は、引用元が「リビンマッチ」であることを必ず明記してください。
引用ルールについて


















