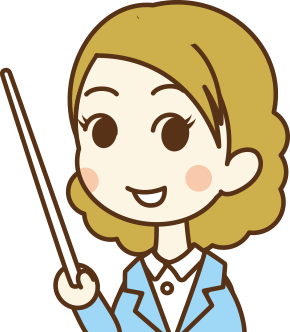住み替え時に利用したい引き渡し猶予とは?売主にもリスクがあるって本当?

不動産を売却するとき、基本的に決済と引き渡しを同時に行う必要があります。
しかし、住み替えで次の住居が見つかっていない場合などは「引き渡し猶予」を設けることで引き渡しを遅らせることができます。
この引き渡し猶予は、買主にとっては代金を支払ったのに物件が手に入らないデメリットがあります。一方で、売主にもリスクがあります。
この記事では、不動産を引き渡す際の猶予期間の基本的なことや、売主のリスクについてわかりやすく解説します。
もくじ
引き渡し猶予とは
引き渡し猶予とは、その名の通り物件の引き渡し期間を猶予してもらうことです。ここではまず、この猶予期間がどのように利用されているのかを確認しましょう。
支払い後引き渡しまで猶予を設けること
不動産売買では、売買契約を売主と買主が締結してから、約1カ月で決済と物件の引き渡しをします。決済と引き渡しは、同日に手続きを行うのが一般的です。
この決済と引き渡しのタイミングがずれる場合、そのずれた期間を引き渡し猶予期間として売買契約に盛り込むことがあります。一般的には、1週間〜10日ほどの期間が設定されることが多く、買主と売主の合意で決められます。
主に売り先行の住み替えで利用される
売主が物件を売却して住み替える方法は、次の2つあります。
- 買い先行:住み替え先の物件を先に購入し、その後売却する
- 売り先行:物件を売却し、その後住み替え先の物件を購入する
買い先行であれば、すでに新しい住居を用意しているため、決済と同時に物件を引き渡せます。買い先行は売却代金を得る前に次の物件を購入するため、資金調達が難しくなるというデメリットがあります。
一方、売り先行の場合、売却が決まった状態で次の住まいを購入するため、資金のめどを立てやすいというメリットがあります。そのため、売り先行で住み替えを行うケースが多いです。
売り先行では、基本的に売却代金で住宅ローンを完済し抵当権を抹消します。その後新たな住まいの住宅ローンを組んで住み替えます。売り先行の場合の流れは以下のとおりです。
- 現住居の売却
- 住宅ローンの完済、抵当権の抹消
- 仮住まい
- 新居の住宅ローン融資を受ける
- 引っ越し
新居の住宅ローンは、売却する物件の住宅ローンを完済しなければ融資してもらえないことがほとんどです。それは一時的に住宅ローンが二重になることで、銀行が推奨する返済比率を大きく超えてしまうためです。返済比率とは、年収に対する住宅ローンの年間返済額の割合のことをいいます。
そのため、売却から新居への引っ越しの間に、仮住まい期間が必要です。仮住まいは、賃貸物件に引っ越すケースが多いですが、当然敷金や礼金などの費用がかかります。
引き渡し猶予とは、この仮住まい期間を避けるためのものです。
買主にリスクがある点に注意
買主からすると、代金を支払ったのに物件の引き渡しを受けられない期間が発生します。
引き渡し猶予の期間が短ければ、売主が住み替えの手続きに間に合わないおそれがあります。しかし、期間が長ければそれだけ買主への負担が増えてしまう点も考慮しなければなりません。
また、引き渡し猶予を設けると同時に、「買い替え特約」を付けるケースが一般的です。買い替え特約では、万が一売主が、新しい住まいの購入ができない、具体的には住宅ローンの審査が否決になった場合などは、物件の売却を解除するという特約です。
この特約があれば、買い替えができなくても、売主はペナルティなしで売買契約を解除できます。買主にとっては、時間や金銭の負担をしたうえにペナルティなしで契約を解除されるので大きなリスクとなります。
このように、引き渡し猶予は買主のリスクが大きい点を理解しておきましょう。
引き渡し猶予のリスクは売主にもある
引き渡しまでに猶予期間を設ける場合、リスクが買主だけでなく売主にも発生します。売り出す前にしっかりリスクを把握しておく必要があります。
買主に敬遠される
引き渡しまでに猶予期間が付いている物件の取引は、買主にとって大きなリスクです。そのため、買主から避けられる傾向にあります。
引っ越し先や引っ越し日が決まっていれば、その旨を伝えておくとよいでしょう。引っ越し先がきちんとあり引っ越しのための期間という主張になるため、買主も受け入れやすくなります。
引き渡しまでの管理責任がある
同日に決済と引き渡しをする場合は、物件の所有権が引き渡しと同時に買主に移ります。
引き渡し猶予がある場合、決済後に所有権は移りますが、物件の管理責任は引き渡しが完了するまで売主が負います。
引き渡しまでに、物件の不具合や災害などで倒損や破損が発生すると、売主が修繕費を負担する必要があります。引き渡しまでに修繕できないなどで、契約内容通りの物件を引き渡せなくなると、契約の無条件解除などのリスクがあります。
また、引き渡しまでの光熱費や固定資産税の負担も売主が負う点にも注意が必要です。
引き渡し猶予の期間が長くなるほど、リスクが高くなるだけでなく、買主とのトラブルに発展するリスクも高くなります。
(固定資産税の納税義務者等)
第三百四十三条 固定資産税は、固定資産の所有者(質権又は百年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする。以下固定資産税について同様とする。)に課する。
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)
値引き交渉されやすい
引き渡しまでに猶予期間を設定していると、買主から値引き交渉をされることが増えます。
猶予期間などの特約がなくても、価格面や条件面で買主から交渉が入るのは珍しくありません。その際に、不動産会社の担当者が優秀だったり、購入希望者が多かったりすると、買主の希望する条件に譲歩する必要はありません。
しかし、引き渡し猶予は売主の一方的な都合であるため、ほとんどのケースで値引き交渉に応じる必要があるでしょう。
交渉が入ることをあらかじめ頭に入れて、売り出し価格を少し高めに設定することをおすすめします。たとえば、2,500万円で売りたいときは、交渉が入ることを想定し、2,700万円で売り出すといった具合です。
希望条件で売却活動を行うために
不動産売却時には、少しでも希望条件で売却したいものです。引き渡し猶予などの希望条件を満たしながら売却を進めるにはどうすればよいでしょうか。
優秀なパートナーをみつけることが重要
引き渡し猶予を付けた物件をトラブルなく売却するには、信頼できる担当者をパートナーにすることが大切です。
買主に不利になる引き渡しまでの猶予期間が付いていても、買主が納得して購入してくれるかは担当者の腕次第ともいえます。また、実力や実績がある担当者なら、説明不足からトラブルが発生することもないでしょう。
引き渡し猶予を理由に値引き交渉してくる買主もいるため、担当者によっては早期売却を優先してしまい、希望する価格で売れないおそれがあります。
そのため、信頼して任せられる自分と相性のよい担当者を選びましょう。
一括査定を利用しよう
不動産会社や担当者を選ぶ際は、複数の不動産会社に査定依頼して、比較検討することが大切です。査定価格だけでなく、次のようなポイントもチェックしましょう。
- 不動産会社の実績
- 口コミや評判
- サービスやアフター
- 担当者の対応
- レスポンスの早さ
査定価格の高さだけで選んでしまうと、売れずに結局値引きしなければならないというリスクもあります。不動産会社や担当者は、総合的に判断して慎重に選ぶことが重要です。
とはいえ、複数の会社に査定依頼するにも時間がかかるものです。そのため、一括査定の利用をおすすめします。一括査定であれば、簡単な入力だけで複数の不動産会社の査定結果を比較できます。
査定結果の比較はもちろん、担当者の対応や誠実さもチェックしましょう。より満足できる不動産売却をするために、ぜひ活用したいサービスです。
引き渡し猶予に関するよくある質問
- 引き渡し猶予はどのようなケースで利用するの?
- 住み替え時に利用します。売却から新居への引っ越しの間に、仮住まい期間が必要です。仮住まいは、賃貸物件に引っ越すケースが多いですが、当然敷金や礼金などの費用がかかります。引き渡し猶予とは、この仮住まい期間を避けるためのものです。
- 売主にはどんなリスクがあるの?
- 買主に敬遠される、引き渡しまでの管理責任がある、値引き交渉されやすいなどのリスクがあります。
関連記事
- 売買契約とは?締結の流れと必要書類や契約解除について解説します。
- 不動産売却の平均期間は?売却スケジュールやタイミングも併せてご紹介
- 家の売却に必要な平均期間は6カ月!期間が長引く売れない物件の特徴とは
- 不動産売却の引き渡し日の流れ!トラブル回避法についても紹介
- 不動産売買における重要事項説明の目的と要点を分かりやすく紹介
- 家の売却にはどのような準備が必要?
- 不動産を売却しやすい時期はいつ?会社選びが重要な理由
- 【初心者必見】家を売る前にすること・やってはいけないことを徹底解説!
- 家が売れてからお金が入るまでの期間は?取引全体のお金の流れや注意点を解説
- 家の売却は内覧で決まる!買主の心をつかむためにやるべき準備と当日の対応
- 家を売るとき、いつまで家に住める?引き渡し日を延ばす方法はある?

大手住宅メーカーの注文住宅販売や不動産テック企業の仲介業務に4年間携わり、不動産取引にかかわった件数は350件以上にわたります。2021年よりリビンマッチコラムの執筆・編集を担しています。皆さんが安心して不動産取引を行えるよう、わかりやすくリアルな情報を発信します。
この記事の編集者
 リビンマッチ編集部
リビンマッチ編集部
リビンマッチコラムでは、むずかしい不動産の事をできる限りわかりやすく、噛み砕いて解説しています。不動産に対するハードルの高いイメージ、とっつきにくい苦手意識を少しでも取り除いて、よりよい不動産取引のお手伝いをさせていただきます。
誤字脱字や事実誤認などございましたら、ぜひともご指摘ください。
運営会社:リビン・テクノロジーズ株式会社(東京証券取引所グロース市場)
人気ワード
老後の住まい (24) 離婚と財産分与 (21) 離婚と住宅ローン (17) 売れないマンション (16) 一括査定サイト (15) 海外移住 (11) 訳あり物件 (11) 家の売却 (11) 家の後悔 (10) 不動産高く売る (9) 実家売却 (9) マンション価格推移 (8) マンションの相続 (8) 移住 (7) アパート売却 (7) 離婚と家 (7) 不動産会社の選び方 (6) マンション売却の内覧 (6) 家の価値 (6) 離婚準備 (6) 売れない家 (5) お金がない (5) 空き家売却 (5) 離婚と家売却 (5) 農地売却 (4) 近隣トラブル (4) マンション買取 (4) 家の解体費用 (4) 売れない土地 (3) サブリース (3) イエウール (3) 不動産価格推移 (3) マンションか戸建てか (2) リビンマッチ評判 (2) シンガポール移住 (2)リビンマッチコラムを引用される際のルール
当サイトのコンテンツはどなたでも引用できます。 引用にあたって事前連絡などは不要です。 コンテンツを引用される際は、引用元が「リビンマッチ」であることを必ず明記してください。
引用ルールについて