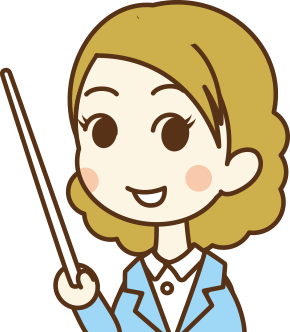不動産売却の引き渡し日の流れ!トラブル回避法についても紹介

不動産の売却は人生で何回も経験することではありません。そのため、物件の引き渡し時にはどのような対応をすればよいか戸惑ってしまう方も多いでしょう。
事前にしっかりと準備をしておくことで、当日はスムーズな引き渡しを行いましょう。
本記事では、引き渡し日の流れや当日に必要な書類を解説します。また、引き渡し時に起こるおそれがあるトラブルも紹介するので、あらかじめ対策をしておきましょう。
もくじ
引き渡し日の流れ
引き渡し当日は慌ただしくなるので、あらかじめ当日の流れを理解し、準備しておく必要があります。
基本的には決済終了後すぐに物件の引き渡しを行うので、決済と引き渡しは同日に行われます。
- 決済場所に集合
- 書類の確認
- 金銭の授受
- 鍵の引き渡し
上記の手順に沿って解説します。
決済場所に集合
買主が住宅ローンを利用している場合は、住宅ローンを利用する金融機関で行うのが一般的です。それ以外には、仲介している不動産会社の事務所などがあります。
通常、決済を行うのは平日の午前中です。平日でないと金融機関がやっていないのと、午前中であれば、トラブルが起きても午後に対応できるからです。
決済場所には、売主と買主のほかに以下の方々が集まります。
- 不動産仲介業者
- 所有権の移転登記を行う司法書士
- 金融機関のローン担当者
また、売主にローンが残っている場合、必要に応じて売主のローン担当者も立ち会う場合があります。
書類の確認
必要な契約書類は通常、不動産仲介業者が作成してくれます。その書類に署名・押印をして契約書類を完成させます。当日持参する必要のある書類は後述します。
その後、司法書士により本人確認が行われます。マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類を持参しましょう。
本人確認が終わると、先ほど完成させた書類や、必要書類を司法書士が確認します。
金銭の授受
司法書士による書類の確認が終われば、次は買主から売主に金銭の支払いがあります。
その金額には、不動産の金額以外にも、固定資産税や都市計画税、管理費、修繕積立金などが日割りで含まれます。
買主が住宅ローンを利用する場合は、この時点で金融機関からの融資が実行され、その一部または全部が売主の指定口座に振り込まれます。
振込手続き後、売主は着金を確認します。通常、数分から数十分ほどで着金が確認できます。
着金が確認でき次第、売主は買主に領収書を発行します。領収書の用紙は通常、不動産仲介業者が用意してくれますが、誰が用意するかはあらかじめ確認しておくとよいでしょう。
鍵の引き渡し
領収書と同時に、鍵や設備の取扱説明書、保証書、建築関係の書類などを引き渡します。鍵は合鍵も含め、保有しているものすべてを引き渡しましょう。
鍵の引き渡しが終わると、買主との取引は終了です。
その後、売主は司法書士への報酬・登記費用、不動産仲介業者の仲介手数料を支払い、領収書を受け取って終了です。
同日中に司法書士が不動産の所有権を売主から買主に変更する手続きを行います。売主に住宅ローンが残っていて不動産に抵当権が付いている場合は、売却金額で住宅ローン完済後に抵当権抹消登記の手続きも行います。
当日に必要な書類
当日に必要な書類はたくさんあります。あらかじめ不動産仲介業者から連絡があると思いますが、引き渡しをスムーズに行うため、十分確認しましょう。
売主が用意しなければいけないもの
引き渡し当日に持っていかなければいけない書類は下記のとおりです。
- 権利証(登記済証・登記識別情報)
- 実印と印鑑証明書(発効後3カ月以内)
- マイナンバーカードや運転免許証などの写真付き身分証明書
- 固定資産評価証明書
- 引き渡す物件の鍵すべて
- 建築確認書
- 測量図、設計図など
- 設備や備品の取扱説明書、保証書
- 物件購入時のパンフレット
- マンションの管理規約など
- 着金を確認できるもの(通帳・キャッシュカード・オンライン端末など)
場合によって必要なもの
上記のほかに、場合によっては必要な書類もあります。
住民票か戸籍の附票
登記簿に記載の住所から住所移転をしている場合には住民票も必要です。印鑑証明書と登記簿の住所が一致していないと本人確認ができないからです。2回以上住所変更している場合は、戸籍の附票が必要です。
戸籍謄本
結婚や離婚により登記簿の氏名と現在の氏名が一致しない場合には戸籍謄本も必要です。
司法書士への報酬・登記費用・不動産仲介会社への仲介手数料
買主から受け取る金額から引かれることが多いので、持参する必要がないことが多いです。しかし、あらかじめ不動産仲介業者に確認しておくことをおすすめします。
抵当権抹消のための書類
ローンの返済が終わっているけど、抵当権の抹消の手続きをしていない場合や、売却金額でローンを完済する場合、抵当権を抹消する必要があります。抵当権が残ったままでは、売却できないと考えましょう。抵当権の抹消は登記変更と一緒に司法書士に依頼します。
抵当権を抹消するために必要な書類は、下記のとおりです。
- 登記申請書
- 登記識別情報または登記済証
- 登記原因証明情報
- 登録免許税
- 抵当権者(金融機関など)の委任状
売主が出席できないとき
売主がどうしても引き渡し日に出席できない場合には、代理人が出席することも可能です。
不動産が共有名義の場合は、その全員の出席が必要です。誰かひとりでも出席できない場合には他の人を代理人にする必要があります。代理人が必要な場合には、以下のような書類が必要です。
- 売主の委任状(自筆と実印の押印)
- 売主の印鑑証明書(発効後3カ月以内)
- 代理人の印鑑証明書(発効後3カ月以内)
- 代理人の実印
- 売主の本人確認書類
- 代理人の本人確認書類
引き渡し時はトラブルが多い?
十分に準備をしている引き渡しでも、思わぬトラブルが起きることがあります。ここでは、その一例を紹介します。トラブルのないスムーズな引き渡しを目指しましょう。
引き渡し日以降に退去をする
売主が引き渡し日やそれ以降に引っ越しをすることは絶対にやめましょう。
引き渡し日に物件を引き渡すことができない場合、違約金を支払わなければいけない場合があります。
特に、新築やリフォーム後に引っ越しを予定していて、新居がまだ完成していない場合、引っ越しが遅れる可能性があります。新居の完成が遅れて、引っ越しが遅れてしまっても、引き渡し日までには確実に済ませられるように日程を調整しましょう。
引き渡し後に不具合を発見した
引き渡し後に最も多いトラブルは、傷や汚れや設備の不具合です。不具合を隠して売却してしまうと後々トラブルに発展してしまう場合があります。些細なことであっても、買主に情報提供する姿勢が大切です。
もし情報提供を怠って後から発覚してしまった場合には、契約不適合責任を負うことになります。修復や売却価格の減額、場合によっては契約の解除が必要なケースもあります。
雨漏りなどで建物以外の家具や家電にまで損害が出た場合には、損害賠償請求にまで発展するかもしれません。
そうならないためにも、気になる点は買主と情報共有しましょう。情報共有は口頭ではなく必ず書面で行うようにします。
トラブルを未然に防ぐために
買主は個人の方である場合が多く、売却価格の交渉や引き渡し日の変更などたくさんの要求をしてきます。そのため、多くのトラブルが想定されます。
対策としては、起こり得るケースを想定して、未然に防ぐことです。そのためには担当者が信頼でき、経験豊富であることが望ましいです。優秀な担当者であれば、トラブルを未然に防いでくれます。たとえトラブルが発生したとしてもしっかりと対応してくれるでしょう。
担当者で失敗しないために、一括査定サイトの利用がおすすめです。一度に複数社へ問い合わせができるため、信頼のできる担当者を選ぶことができます。より満足度が高い不動産売却ができるでしょう。
不動産の引き渡しに関するよくある質問
- 引き渡しと決済はなぜ平日の午前中に行われる?
- 平日でないと金融機関がやっていないのと、午前中であれば、トラブルが起きても午後に対応できるからです。
- 引き渡し日のトラブルを回避するには?
- トラブル事例などを把握し、信頼できる担当者を見つけましょう。
関連記事
- 売買契約とは?締結の流れと必要書類や契約解除について解説します。
- 不動産売却の平均期間は?売却スケジュールやタイミングも併せてご紹介
- 家の売却に必要な平均期間は6カ月!期間が長引く売れない物件の特徴とは
- 不動産売買における重要事項説明の目的と要点を分かりやすく紹介
- 家の売却にはどのような準備が必要?
- 不動産を売却しやすい時期はいつ?会社選びが重要な理由
- 住み替え時に利用したい引き渡し猶予とは?売主にもリスクがあるって本当?
- 【初心者必見】家を売る前にすること・やってはいけないことを徹底解説!
- 家が売れてからお金が入るまでの期間は?取引全体のお金の流れや注意点を解説
- 家の売却は内覧で決まる!買主の心をつかむためにやるべき準備と当日の対応
- 家を売るとき、いつまで家に住める?引き渡し日を延ばす方法はある?

大手住宅メーカーの注文住宅販売や不動産テック企業の仲介業務に4年間携わり、不動産取引にかかわった件数は350件以上にわたります。2021年よりリビンマッチコラムの執筆・編集を担しています。皆さんが安心して不動産取引を行えるよう、わかりやすくリアルな情報を発信します。
この記事の編集者
 リビンマッチ編集部
リビンマッチ編集部
リビンマッチコラムでは、むずかしい不動産の事をできる限りわかりやすく、噛み砕いて解説しています。不動産に対するハードルの高いイメージ、とっつきにくい苦手意識を少しでも取り除いて、よりよい不動産取引のお手伝いをさせていただきます。
誤字脱字や事実誤認などございましたら、ぜひともご指摘ください。
運営会社:リビン・テクノロジーズ株式会社(東京証券取引所グロース市場)
人気ワード
離婚で家を財産分与 (27) 老後の住まい (24) 売れないマンション (16) 一括査定サイト (15) 離婚と住宅ローン (13) 海外移住 (11) 訳あり物件 (11) 家の売却 (11) 家の後悔 (10) 不動産高く売る (9) 実家売却 (9) マンション価格推移 (8) マンションの相続 (8) 移住 (7) アパート売却 (7) 不動産会社の選び方 (6) マンション売却の内覧 (6) 家の価値 (6) 離婚と家 (6) 売れない家 (5) お金がない (5) 空き家売却 (5) 離婚準備 (5) 離婚と家売却 (5) 農地売却 (4) 近隣トラブル (4) マンション買取 (4) 家の解体費用 (4) 売れない土地 (3) マンションか戸建てか (3) サブリース (3) イエウール (3) 不動産価格推移 (3) リビンマッチ評判 (2) シンガポール移住 (2)リビンマッチコラムを引用される際のルール
当サイトのコンテンツはどなたでも引用できます。 引用にあたって事前連絡などは不要です。 コンテンツを引用される際は、引用元が「リビンマッチ」であることを必ず明記してください。
引用ルールについて